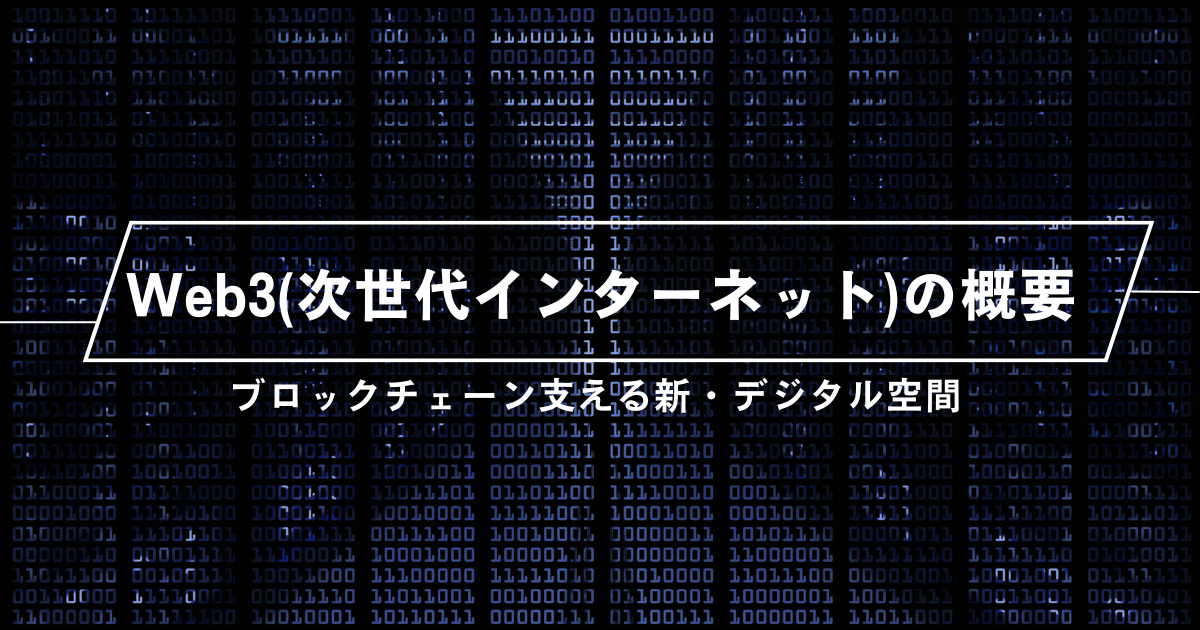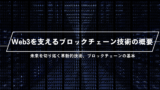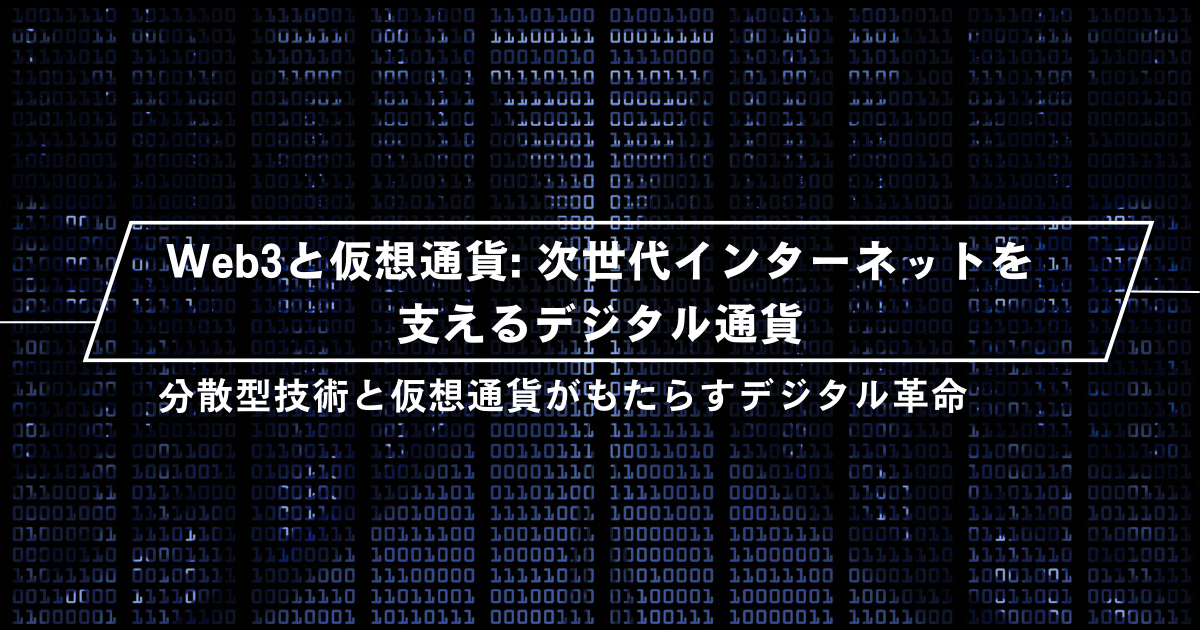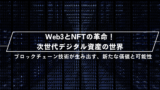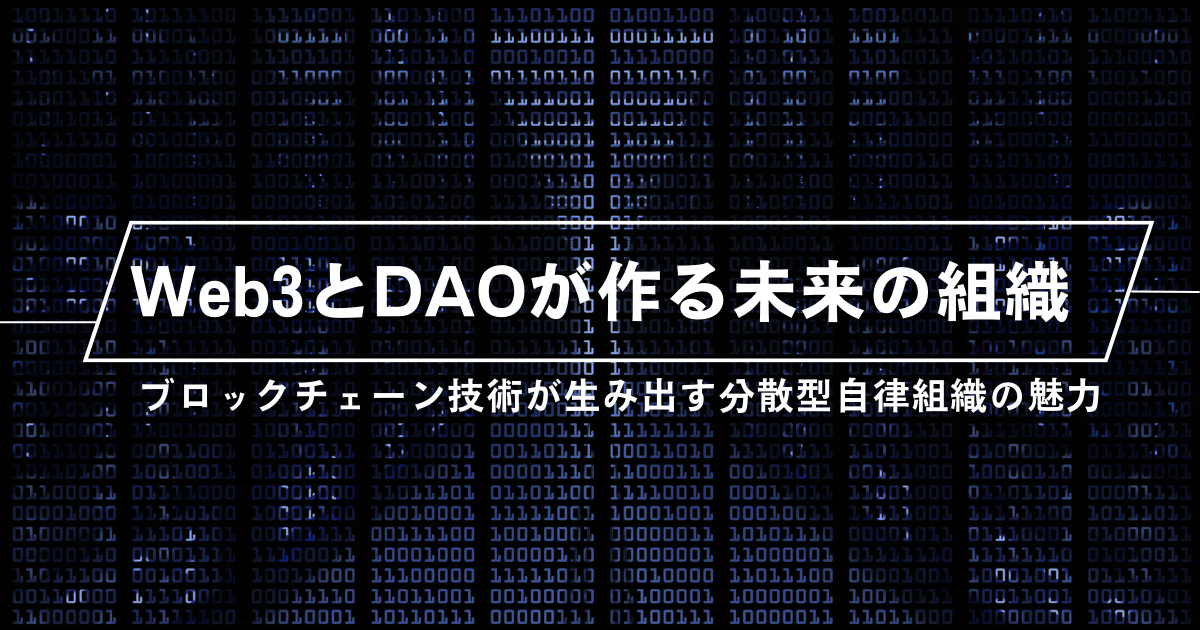最近は「Web3」というキーワードを耳にする機会が増えてきました。WEB3は次世代のインターネットと呼ばれており、ブロックチェーン技術を基盤とし、「分散型インターネット」と定義されています。この記事では、Web3の概要から技術要素、メリット・デメリット、日本の法規制、プロジェクト事例、利用するためのツール、将来展望について解説します。
Web3の概要
Web3の概念がいつ始まったかは諸説ありますが、本サイトでは仮想通貨の1つであるイーサリアム共同設立者であるギャビン・ウッド氏が提唱した2014年と定義します。Web3(Web3.0)とは、その名の通り、Web1.0,Web2.0に次ぐ次世代インターネットの包括的な概念です。まずはWeb1.0,Web2.0,Web3.0それぞれについて、概要を比較してみましょう。
| web1.0 | web2.0 | web3.0 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 静的コンテンツ | 対話型 | 分散型自律 |
| 形態 | 読み取り専用な静的ページ | 読み書き可能(SNS,ブログなど) | 分散型アプリケーション |
| データ管理 | サイトオーナーが管理(オンプレミス主体) | サイトオーナーが管理(クラウド主体) | ブロックチェーンに基づいた分散管理 |
| ユーザー参加 | サイト閲覧者 | コンテンツ作成、共有者 | コミュニティへの参加・貢献者 |
| セキュリティ | 基本的なセキュリティ | より強化されたセキュリティ | 高度な暗号技術 |
| マネタイズ | 広告・購読・eコマース | ターゲティング広告など | 仮想通貨,NFT,マイクロペイメント |
ブロックチェーン技術との関連
ブロックチェーン技術は、暗号化されたデータを分散した台帳に記録することで、改ざんやハッキングのリスクを軽減し、セキュリティを高めます。この技術は、ビットコインをはじめとする仮想通貨や、イーサリアムのスマートコントラクトなどで活用がはじまっています。
Web3は、ブロックチェーン技術を用いて、従来の集権的なWeb環境から分散型(decentralized)のものに変革することを目指しています。
分散型インターネットの概念
分散型インターネットの概念は、サイバー空間における権力や資源を均等に分散させることを目的としています。これにより、GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)などの巨大企業が独占しているデータやサービスを、個々のユーザーや組織が自由に活用できるようになります。Web3は、この分散型インターネットを実現するためのプラットフォームとなることを目指しています。
Web3の技術要素
Web3の技術要素には、スマートコントラクト、分散型アプリケーション(DApps)、仮想通貨とトークンがあります。
スマートコントラクト
スマートコントラクトは、イーサリアム上で動作する自動化された電子契約です。これにより、仲介者を介さずに、双方向の取引ができます。スマートコントラクトは、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)などの分野で広く利用されており、Web3の中核的な技術要素となっています。
分散型アプリケーション (DApps)
DAppsは、分散型インターネット上で動作するアプリケーションです。これらのアプリケーションは、従来の集権型プラットフォーマーを排除し、ユーザー間で直接やり取りができるように設計されています。DAppsは、DeFiやNFT、DAO(分散型自律組織)などのプロジェクトで活用されています。
仮想通貨とトークン
Web3の世界では、仮想通貨やトークンが重要な役割を果たしています。イーサリアムのETHや、その他のERC-20規格に準拠したトークンは、分散型アプリケーションやスマートコントラクトでの取引に使用されます。また、NFTはデジタル資産の所有権を表す非代替性トークンであり、アートやゲームアイテムなどの分野で活用されています。
Web3のメリットとデメリット
Web3は、ブロックチェーン技術を活用することで、データの改ざんや流出のリスクを軽減し、プライバシーとセキュリティを向上させます。これにより、ユーザーは自分のデータをより安全に管理できるようになります。一方で様々な課題もあります。下表にWEB3に関する項目についてメリットとデメリットをまとめました。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 分散型システム | 中央集権的な統制がなく、ユーザーが自由に情報や資産をやり取りできる。 | 分散型のため、悪意のあるユーザーや詐欺師に対する対策が難しい場合がある。 |
| セキュリティ | ブロックチェーン技術により、改ざんが非常に困難である。 | まだ新しい技術であるため、未知のセキュリティリスクが存在する可能性がある。 |
| 所有権の管理 | スマートコントラクトを利用して、所有権を明確に管理できる。 | 初心者にはスマートコントラクトの理解や使用が難しい場合がある。 |
| データプライバシー | ユーザーが自分のデータを管理し、プライバシーを保護できる。 | 完全な匿名性がないため、取引履歴を追跡される可能性がある。 |
| ブロックチェーンの取引手数料 | トランザクションによるネットワーク負荷に応じて報酬が得られる。 | トランザクション料が高騰することで、利用者にコスト負担がかかる。 |
| 柔軟性 | 様々な分野に応用が可能で、新しいビジネスチャンスが広がる。 | 技術的な障壁が高いため、一般の人々が利用するのには敷居が高い場合がある。 |
| 開発の進化 | オープンソースであるため、世界中の開発者が技術を進化させていく。 | 未熟な開発者による不安定なプロジェクトが増える可能性がある。 |
Web3と日本の法規制
Web3の普及に伴い、日本における法規制も変化しています。経産省が産業金融政策の一環として、「大臣官房Web3.0政策推進室」を設置し、様々な検討を行っています。
2022年12月には、「Web3.0事業環境整備の考え方」という75ページにもわたるレポートを発表し、今後のWeb3を活用した取り組みの検討を行っています。
仮想通貨に関する法律
日本では、仮想通貨やトークンに関する規制が整備されており、取引所や発行事業者は適切な許認可を受ける必要があります。また、暗号資産の税制も整備されており、所得税や消費税が適用されます。
金融庁PDF資料「暗号資産(仮想通貨)に関連する制度整備について」
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/20210407_seidogaiyou.pdf
スマートコントラクトと法的取扱い
スマートコントラクトは、自動化された契約として機能しますが、法的な取扱いに関してはまだ明確ではありません。今後、スマートコントラクトが一般的になるにつれて、法規制やガイドラインが整備されることが期待されています。
プライバシーに関する法律
Web3は、プライバシーとセキュリティを重視していますが、日本のプライバシー保護法や個人情報保護法との整合性が課題となります。今後の法規制の動向に注目が集まっています。
Web3プロジェクトの事例
Web3の技術を活用したプロジェクトには、デフィ(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、DAO(分散型自律組織)などがあります。
NFT(非代替性トークン)
NFTは、デジタルアートやゲームアイテムなどの所有権を証明するトークンです。OpenseaやFoundationなどのマーケットプレイスでは、NFTの売買が行われています。
DAO(分散型自律組織)
DAOは、スマートコントラクトを活用して組織の運営を自動化する試みです。AragonやMolochDAOなどのプロジェクトが、企業やコミュニティの運営を効率化し、参加者間での意思決定を分散化しています。
デフィ(分散型金融)
DeFiは、スマートコントラクトを活用して、従来の金融サービスを分散型に再構築する試みです。AaveやCompoundなどのプロジェクトが、貸付や預金、投資などのサービスを提供しています。
Web3を利用するためのツール
Web3は、分散型インターネットを構築するための新しいテクノロジーパラダイムであり、ブロックチェーンやスマートコントラクトを含む様々なテクノロジーが利用されています。Web3を利用するためのツールは多岐にわたりますが、ここでは以下の3つのカテゴリに分けて説明します。
ブロックチェーンウォレット
ブロックチェーンウォレットは、暗号資産を管理・送受信するためのツールです。例えば、Metamask(メタマスク)は、初心者にも使いやすいブラウザ拡張機能のウォレットです。Metamaskをインストールすると、ウェブブラウザ上でイーサリアムやその他のERC20トークンを管理・送受信することができます。
ブロックチェーンエクスプローラー
ブロックチェーンエクスプローラーは、ブロックチェーン上のトランザクションやアドレス、スマートコントラクトなどの情報を閲覧・検索することができるウェブサイトです。例えば、Etherscan(イーサスキャン)は、イーサリアムブロックチェーンを調べるためのエクスプローラーで、トランザクションの詳細やアドレスの残高などを簡単に調べることができます。
分散型アプリケーション (DApps)
分散型アプリケーションは、ブロックチェーン技術を活用したアプリケーションです。例えば、Uniswap(ユニスワップ)は、イーサリアム上で動作する分散型取引所(DEX)で、ユーザーはウォレット(例: Metamask)と連携させることで、暗号資産の交換や流動性プールへの参加などができます。
これらのツールを利用しながら、Web3やブロックチェーン技術に慣れ親しんでいくことができます。
Web3の将来展望
Web3は、分散型インターネットの実現を目指しており、今後のインターネットの進化に大きな影響を与える可能性があります。しかし、技術的な課題や法規制の整備が進むまで、その普及にはまだ時間がかかると考えられます。
本サイトでは今後のWeb3の発展に期待しつつ、動向を追いかけ適時共有していきたいと考えています。
本記事は現在編集中です。本記事についてのご意見・ご要望は、お問い合わせページからご連絡をお願いします。